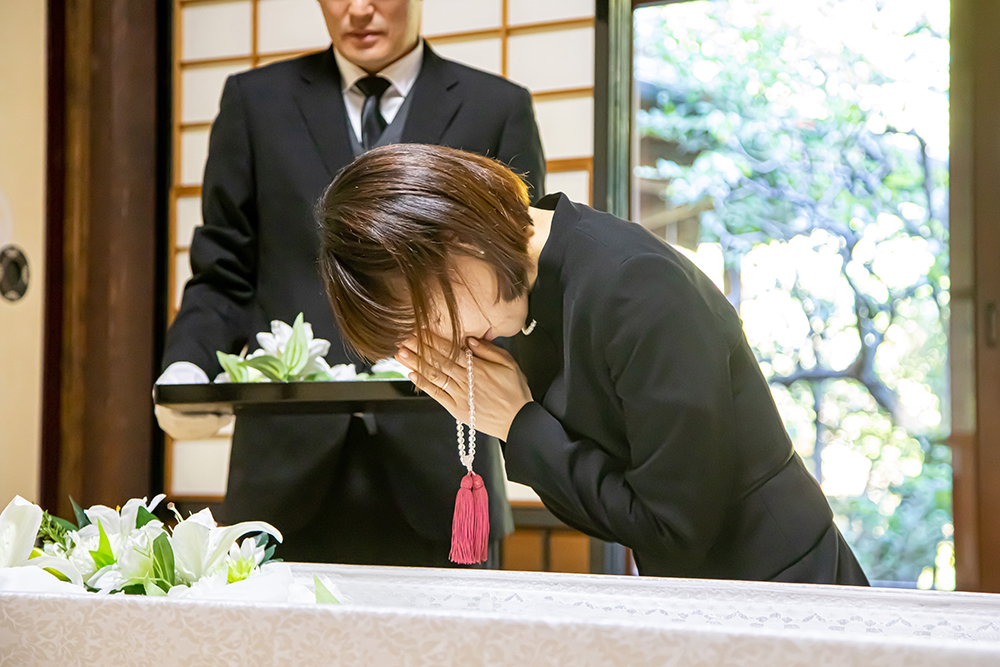大切な家族を失ったとき、深い悲しみの中でも進めなければならない手続きがあります。高砂市では、死亡に関する各種手続きをスムーズに行うためのサポート体制が整備されています。しかし、期限が定められているものもあるため、なかなかゆっくりできないのが現実です。
本記事では、高砂市で家族が亡くなった際に必要となる手続きを、期限別に整理して詳しく解説していきます。手続きには法的な期限が定められているものが多いため、優先順位を明確にして計画的に進めていきましょう。
速やかに行う手続き(死亡後すぐ〜7日以内)
死亡後に速やかに行うべき手続きとして、以下の3つがあります。
・死亡届の提出と火葬許可証の取得
・葬儀社への連絡と斎場の予約
・親族や関係者への連絡
それぞれ詳しく見てみましょう。
死亡届の提出と火葬許可証の取得
家族が亡くなったとき、最初に行う公的手続きが死亡届の提出です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する法的義務があります。国外で亡くなった場合は、3か月以内となっています。
死亡届の提出先は、市民窓口課です。提出する際には、医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要となります。病院で亡くなった場合は医師から死亡診断書が発行され、それ以外の場所で亡くなった場合は警察医などによる死体検案書が発行されます。
なお、届出人となれるのは、以下の条件を満たす人です。
・親族
・同居者
・家主
・地主
・家屋管理人
・土地管理人
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。火葬許可証は、火葬場で火葬を行う際に必要不可欠な書類となりますので、大切に保管してください。火葬後には火葬場から埋葬許可証が交付され、納骨の際に必要です。
葬儀社への連絡と斎場の予約
葬儀の準備も速やかに進める必要があります。予約は葬儀社を通じて行うことが一般的ですが、個人で直接申し込むことも可能です。なお、斎場の使用料は、高砂市民の場合と市外居住者で異なる料金設定となっています。
火葬の時間帯は午前と午後に分かれており、希望の時間帯を選択できますが、混雑状況によっては希望に添えない場合もあります。特に友引明けの日は混雑することが多いため、早めの予約がおすすめです。
親族や関係者への連絡
故人の親族や勤務先、友人知人への連絡も速やかに行う必要があります。特に遠方の親族には、葬儀の日程が決まり次第、早めに連絡することが大切です。
勤務先への連絡では、死亡退職の手続きについても確認してください。退職金や最終給与の支払い、社会保険の手続きなど、会社側で必要な手続きがあります。また、社内規定により弔慰金が支給される場合もあるため、人事部門に確認しましょう。
14日以内に行う手続き
死後14日以内、つまり2週間以内に行う手続きとして、次のものがあります。
・年金受給停止の手続き
・世帯主変更届の提出
・介護保険資格喪失届と保険証の返却
中には手続きが不要な場合もありますが、基本的には対応できるように準備しておいてください。それぞれ解説します。
年金受給停止の手続き
故人が年金を受給していた場合、年金事務所への死亡届の提出が必要となります。国民年金の場合は死亡後14日以内、厚生年金の場合は10日以内に届出を行わなければなりません。管轄する年金事務所は加古川年金事務所です。
届出が遅れると、年金の過払いが発生し、後日返還を求められることがあります。早めの手続きにより、トラブルを避けることができるでしょう。手続きの際は、以下の書類を用意してください。
・年金証書
・死亡診断書の写し
・届出人の身分証明書
また、未支給年金がある場合、生計を同じくしていた遺族が請求することができます。
世帯主変更届の提出
故人が世帯主だった場合、世帯主変更届を14日以内に提出しなければなりません。市民窓口課で手続きを行い、新しい世帯主を届け出ます。
この手続きは、世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合に必要です。一方、残された世帯員が1人の場合や、15歳未満の子どもと親権者のみの場合は、自動的に世帯主が決定されるため、手続きは不要です。
介護保険資格喪失届と保険証の返却
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失手続きが必要です。高砂市では、死亡届の提出により自動的に資格喪失となりますが、介護保険被保険者証の返却は14日以内に行わなければなりません。
介護サービスを利用していた場合、サービス事業者への連絡も忘れずに行ってください。また、介護保険料の精算も必要となります。死亡した月の前月分まで納付する必要があり、年金から天引きされていた場合は、後日精算されることになります。
1か月以内に行う手続き
1か月以内に行う手続きとして、次のようなものがあります。
・雇用保険受給資格者証の返還
・公共料金等の名義変更
・運転免許証の返納
詳しく見てみましょう。
雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険を受給していた場合、受給資格者証を1か月以内にハローワークに返還する必要があります。高砂市を管轄するハローワークは、ハローワーク加古川です。
返還の際は、死亡診断書の写しや届出人の身分証明書が必要となります。受給期間中に死亡した場合、未支給分については一定の要件を満たす遺族が受給できる場合があります。詳細はハローワークで確認してください。
公共料金等の名義変更
電気やガス、水道などの公共料金については、速やかに契約者の名義変更または使用中止の手続きを行う必要があります。特に口座振替を利用している場合、故人の口座が凍結される前に手続きを完了させましょう。
高砂市の上下水道については、市役所上下水道部で手続きを行います。電気やガスについては、それぞれの供給会社に連絡し、手続きを進めます。名義変更の場合は、新契約者の情報が必要です。また、口座振替を利用する場合は、新たに口座振替依頼書の提出が必要です。
運転免許証の返納
故人が運転免許証を所持していた場合、最寄りの警察署に返納します。返納は義務ではありませんが、紛失による悪用を防ぐためにも返納することをおすすめします。高砂市の場合、高砂警察署で手続きが可能です。
なお、運転免許証は身分証明書としても使用されることが多くあります。各種手続きで必要な場合は、コピーを取っておくとよいでしょう。
3か月以内に行う手続き
死後3か月近くになると、相続関連の手続きも完了させる必要が出てきます。具体的には、以下の2つを進めましょう。
・相続放棄・限定承認の申述
・相続財産の調査と遺産分割協議の開始
詳しく解説します。
相続放棄・限定承認の申述
相続財産に多額の負債が含まれる場合、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。高砂市の場合は神戸家庭裁判所姫路支部が管轄となります。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。一度相続放棄をすると撤回できないため、慎重に検討しましょう。相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることも可能です。
限定承認は、相続財産の範囲内で負債を弁済する方法で、相続人全員で行う必要があります。手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続財産の調査と遺産分割協議の開始
相続手続きを進めるにあたり、3か月以内に相続財産の全容を把握することが重要です。預貯金や不動産、有価証券や生命保険、負債などを漏れなく調査します。
金融機関に相続発生の連絡をすると口座が凍結されます。凍結後は、相続人全員の同意がなければ払い戻しができなくなるため、葬儀費用などの必要資金は事前に確保しておいてください。なお、2019年7月から、一定額までは単独で払い戻しが可能となる制度も導入されています。
不動産については、法務局で登記簿謄本を取得し、所有権の状況を確認します。市役所で固定資産評価証明書を取得し、評価額を把握することも必要です。
4か月以内に行う手続き
4か月以内に行う手続きは、主に税金関係のものとなります。
・準確定申告
・所得税の納付または還付請求
それぞれ詳しく解説します。
準確定申告
故人に所得があった場合、相続人が準確定申告を行う必要があります。準確定申告とは、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要がある手続きです。高砂市の場合は加古川税務署に申告します。
準確定申告が必要となるのは、故人が以下の条件を満たす場合です。
・個人事業主だった場合
・不動産所得があった場合
・給与所得が2,000万円を超えていた場合
・2か所以上から給与を受けていた場合
・医療費控除などの還付申告をする場合
申告書の作成は複雑な場合が多いため、税理士に依頼することも検討してください。特に事業所得がある場合や、不動産の譲渡所得がある場合は、専門的な知識が必要となります。
所得税の納付または還付請求
準確定申告の結果、納税が必要な場合は4か月以内に納付しなければなりません。一方、源泉徴収されていた税金が多い場合や、医療費控除などの適用により還付を受けられる場合もあります。
還付金は相続財産として扱われるため、相続人間で分配する必要があります。相続人が複数いる場合は、代表者を決めて手続きを行い、後日分配することが一般的です。
納税資金が不足する場合は、延納制度の利用も検討できます。ただし、利子税が発生するため、可能な限り期限内に納付することが望ましいでしょう。
10か月以内に行う手続き
死後手続きのほぼ最後に行うのが、10か月以内に行う以下の手続きです。
・相続税の申告と納付
・不動産の相続登記
上記の2つは、忘れているとペナルティが課せられる手続きです。それぞれ詳しく解説します。
相続税の申告と納付
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付を行う必要があります。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える相続財産がある場合に申告が必要です。
相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。加古川税務署に申告書を提出しましょう。財産評価や各種特例の適用判断など専門的な知識が必要となるため、税理士に依頼することが一般的です。
なお、相続税には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、各種特例を適用することで相続税を大幅に軽減できる場合があります。特例の適用には要件があるため、早めに税理士に相談し、適用可能な特例を確認することが重要です。
不動産の相続登記
2024年4月から相続登記が義務化されており、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。ただし、遺産分割協議が成立している場合は、早めに登記を完了させるのがおすすめです。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。高砂市の場合、神戸地方法務局加古川支局です。必要書類は、以下のとおりです。
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・固定資産評価証明書 など
登記手続きは複雑なため、司法書士に依頼することも検討してください。司法書士に依頼する場合、報酬のほかに登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要となります。
期限のない手続き
ここまで紹介した以外にも、次の手続きをしなければなりません。
・クレジットカードの解約
・パスポートの返納
・デジタル遺品の整理
近年はデジタル遺品と呼ばれるものの整理が必須の時代となりました。SNSアカウントやメールアドレス、オンラインストレージなどのことです。各サービスにより手続きが異なりますが、多くの場合、死亡証明書と相続人であることの証明が必要となります。
重要なデータがある場合は、削除前にバックアップを取ることをおすすめします。また、パスワードが不明な場合は専門業者に依頼することも検討できますが、費用と時間がかかる点には注意が必要です。
高砂市のおくやみハンドブックを活用しよう
高砂市が作成している「おくやみハンドブック」には、期限別の手続き一覧が掲載されています。このハンドブックを活用することで、手続きの優先順位を明確にし、漏れなく手続きを完了させられるでしょう。
市役所で配布されているほか、市のWebサイトからもダウンロード可能です。チェックリスト形式になっているため、完了した手続きにチェックを入れながら進めることで、進捗状況を管理できます。
また、2025年1月20日から「おくやみコーナー」の運営が開始されました。このコーナーでは、死亡に伴う市役所での手続きをワンストップで案内しており、効率的に手続きを進めることができます。
利用は事前予約制となっており、電話またはインターネットから予約が可能です。予約時に故人の情報を伝えることで、当日必要な書類の案内を受けることができます。専門スタッフが手続きの優先順位や期限についても丁寧に説明してくれるため、初めての方でも安心して手続きを進められます。
これらを活用し、期限内に手続きを完了させるようにしてください。
まとめ
家族が亡くなった際の手続きは、期限を意識した計画的な進行が不可欠です。死亡届の7日以内提出から始まり、10か月目までは重要な期限が続きます。特に相続放棄と税務申告の期限は厳格で、遅れると権利を失ったり追徴課税を受ける可能性があります。十分注意しましょう。
おくやみコーナーやおくやみハンドブックを活用しながら、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家の力を借り、確実に手続きを完了させることも重要です。
大切な家族を亡くされた悲しみの中での手続きは精神的にも負担が大きいですが、ひとつずつ着実に手続きを進め、わからないことがあれば遠慮なく相談するようにしてください。